皆さん、こんにちは。小学生姉妹と、1歳ベビーを子育て中のはみっく編集部ライターです。
わが家の長女は現在小学6年生。ここ一年ほどで、一気にスマホを持つ子が増えたな…という印象があります。我が家は、遅い時間帯の習い事に通わせることになったのをきっかけに、長女には小学4年生からスマホを持たせていますが、ママ友からは「やっぱりうちも買ってあげるべき?」といった相談をよく受けるようになってきました。

今回の記事を書くにあたり、改めて周りのママたちに話を聞いてみると、「持たせてよかった派」と「まだ早い派」で、意見は真っ二つ!
ということで、今回は、「スマホを持たせない」という選択をした場合、どんなところが困るのか、どう工夫すればいいのかを、私自身の体験やママ友のリアルな声を交えながらまとめてみました。
|
関連記事▽ |
スマホがないと困る?不便なことってどんなこと?

[画像引用:ICT教育ニュース ]
ICT教育ニュースの記事によると、中1時点でのスマホ所有率は81.7%。小6時点では54.1%なので、中学入学を機に、スマホを購入するお家が多いことがデータからもわかります。ここまでスマホを持っている子が増えている状況では、スマホを持たせないことで不便なことも出てくるようで…。
友達とのやりとりやコミュニケーションに支障がでる

現在小6の長女ですが、小学5年生あたりから「クラスのライングループ」ができるようになり、イベント事についての話し合いや宿題についてなど、SNSを使って友達同士で情報を共有するようになりました。スマホを持っていない子や、SNSをやっていない子には、翌日学校で伝えるなど、子どもたちなりに情報共有の対策をしているようではありますが、中には決定事項として事後報告されているパターンもあるようで、心配になることもしばしば。(先日は運動会の応援団の打ち上げの日程がライングループで決定されていました。)
スマホを持っている派が大多数になっていることで、持っていない子は少数派として意見が言いづらい環境になる場合もあるのかもしれません。
中学生になると、部活の連絡もSNSで一斉連絡になる場合が多いとのことなので、スマホを持たせないのであれば、そのあたりの対策も考えておく必要があると言えます。
学習アプリがすぐ使えない

中学生のお子さんを持つママ友から聞いたのは、「学習面での不便」でした。大手学習塾では塾生向けのアプリや動画配信サービスを行っているところも多く、自宅学習にはアプリで授業の復習を、というケースも少なくないのだとか。そのママ友のおうちでは、自宅用タブレットを使用して学習をしているそうですが、お子さんからは「自分のスマホを使っている子は隙間時間や移動中にアプリが使えていて羨ましい」と言われるため、スマホの購入を検討しているのだそうです。(「スマホが欲しいから、勉強を言い訳にしているのかも?とも思うし迷っている」とのことでした。)
防犯面でもやや不安かも?

高学年になってくると、スマホを持っている子も増えてくることから、習い事も少し遅い時間帯になってきたり、友達同士でのおでかけの範囲も広くなってきます。うちの娘達もショッピングモールでの買い物や映画など、友達同士で約束をしてくるようになりましたが、スマホがないと、友達とはぐれて迷子にならないか、帰り道で不審者に遭遇したりしないか、など、いろんな心配がでてきますよね。メッセージのやり取りができるGPSや、キッズ携帯など、他の防犯アイテムもあるので、スマホを持たせないのであれば、代わりになるものを準備してもいいかもしれません。
スマホを持たせない親はどうしてる?工夫とアイデア
さきほどの項目で書いたように、スマホを買わない選択をする場合、実際の生活の中で困ることが出てきます。スマホを持たせていないご家庭は、そのあたりをどのように対策しているのかリサーチしてみました。
自宅Wi-Fi専用端末で十分なことも

ママ友の中に多かったのが、学校や部活の連絡用に親のお下がりスマホをWi-Fi専用端末として利用しているパターンでした。「緊急性が高い連絡ってほとんどないから、自宅で確認するだけでもそこまで困ってなさそうだよー!」と話すママ友も。持ち歩けるスマホの便利さは確かにありますが、メッセージのやり取りだけがスマホを持ちたい理由、という子なら、これである程度こと足りるようです。
GPSやキッズ携帯などスマホ以外の選択肢も
前の項目でも書いたように、最近は、スマホがなくても連絡が取れるようなデジタルデバイスがたくさん発売されています。例えば、音声メッセージの送受信ができるGPS端末や、キッズ携帯のプラスメッセージ機能など、位置情報を送信するだけではない、プラスの機能が充実してきています。
スマホを使わずに、防犯面の強化や、家族とのリアルタイムなやりとりを望むのであれば、そういったデジタル端末の導入をかんがえてみるのも手かもしれません。
Hamic MIEL nicoを使ってみた

わが家では、スマホを使い始める前の半年間、お試しでHamic MIELS nicoを導入しました。電話番号の付与がないため、LINEは使えないのですが、ネット検索やアプリのインストールは可能で、機能としては一般のスマホ同様の便利さ。スマホとの付き合い方や、ネットリテラシーを学んでから、スマホデビューができたのも、親としては安心材料になりました。
ちなみに、長女使用後のHamicMIELS nicoは、現在次女が使用しており、「学校に行く際のマナーモードのOn/Offや、毎日の充電といった管理がきちんとできるようになったら、スマホデビューしてもいいよ!」という約束になっています。
スマホが欲しい子どもを納得させるには?
工夫をしたり、スマホがなくても大丈夫なように対策をしたところで、子どもの「スマホが欲しい」という気持ちは変えられない場合も。なるべく反発を抑えられるよう、ママ友たちはこんな対策をしているのだそうです!
「こうなったら買う」と約束しておく
「なんで自分だけスマホを買ってくれないの!?」と反発されるのが面倒で折れそう、というママ友に、別のママ友がアドバイスしていたのが、「高校生になったら」「学年で成績が上位なら」と条件付きの見通しを示すという方法でした。
 ちなみに、そのママ友は「うちは英検〇級合格したらって約束にしてる」のだとか。ゴールが見えるだけで、子どもの気持ちも落ち着く上、スマホが欲しいから頑張る、という動機になる場合もあるのなら、やってみない手はないなと感じました。
ちなみに、そのママ友は「うちは英検〇級合格したらって約束にしてる」のだとか。ゴールが見えるだけで、子どもの気持ちも落ち着く上、スマホが欲しいから頑張る、という動機になる場合もあるのなら、やってみない手はないなと感じました。
親の「持たせない理由」を伝える
スマホを買わないと決めているママたちに理由を聞くと、「上の子は高校からスマホを持たせたから下の子にそれより早く持たせるのは不公平な気がする」「反抗期で会話が減ってるのに、スマホを持ち始めたらさらにコミュニケーションの機会が減りそうで怖い」「通信料もかかるし、スマホデビューはなるべく遅らせたい」など、各ご家庭で様々な事情があることがわかりました。
子どもの「スマホ買って!」を「まだ早いから」とあしらうのではなく、ご家庭なりの理由を整理して共有することで、打開策が見つかったり、子どもに納得してもらいやすくなるのかもしれません。
まとめ:スマホデビューに正解なし!
小学校高学年のお子さんの、スマホ問題について調べてみた本記事、いかがだったでしょうか?
ママ友たちの話を聞いて、それぞれに事情や考えがあり、スマホを買うか買わないか・持たせ始めるタイミングなど、正解は一つじゃないということを改めて感じました。
「うちの子にはまだ早い気がするけど、子どもは欲しがってるし、中学生になったら、みんな持ってるらしいし…」と悩まれているご家庭は、「なぜスマホは必要ないと感じるのか」「なぜスマホが欲しいのか」もう一度家族で話し合って、我が家なりの落とし所を探してみて下さいね。
最新記事一覧
関連記事一覧
-
-

- 位置情報の共有はどこまで信じられる?先輩ママたちが実感した「正確さより安心感」のGPS活用法
-
-
-

- 小学生にモバイルバッテリーを持たせるなら?発火ニュースが心配なママ必見の安全な使い方と注意点
-
-
-
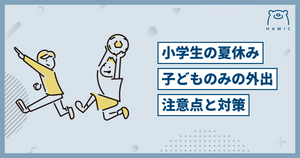
- 【夏休み】小学生の「子どもだけ」おでかけは何歳からOK?映画館・プール・お祭りetc…注意点&親ができる対策まとめ
-
-
-
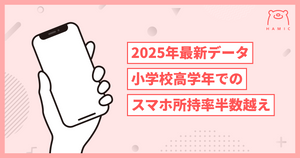
- 高学年の子どものスマホ所持率が半数超え!?小学生ママが見る【2025年最新データ】
-
-
-
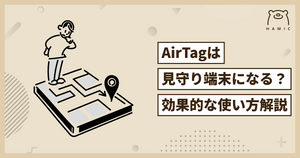
- AirTagは子どもの見守りGPS代わりに使うと危険!?効果的な使い方を小学生ママが教えます
-
-
-
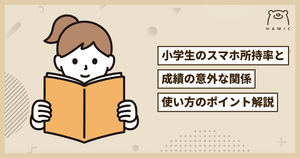
- 小学生のスマホ所持率5割越え!なのに…スマホを使うと学力低下?!使い過ぎを防ぐHamicMIELS nicoで安心・安全に
-







